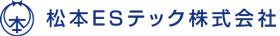2025年の育児・介護休業法改正~仕事と家庭の両立を目指して~

少子高齢化が進む中、「家族の介護と仕事の両立」「子どもの養育と仕事の両立」を、行政や企業が一体となってサポートすることが、ますます重要になっています。2025年は、育児や介護をしながら働く人をより一層支えるため「育児・介護休業法」が大きく改正されました。この記事では、4月と10月の2回分けて改正された育児・介護休業法の主な内容をご紹介します。
2025年:育児・介護休業法改正の目的と方向性

厚生労働省は「育児や介護を理由に、仕事を辞めなければならない人を減らすこと」を目的に、企業と働く人の双方が、柔軟に働ける仕組みを整えるための方針を掲げています。2025年の法改正では、現行の休暇制度の取得要件や利用者の拡充に加え、育児・介護期の労働条件の個別配慮など、実際の職場でより利用しやすい制度を目指した内容になりました。
2025年4月改正:子の看護休暇が「子の看護等休暇」に変わりました

2025年4月の改正で「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」へと名称が変更され、取得できる対象範囲と、休暇の取得事由が拡大されています。2025年3月31日まで適用されていた旧「育児・介護休業法」での「子の看護休暇」は「子どもの病気やけが」「インフルエンザの予防接種」「子の健康診断」など、主に「子の看護」に関する事由のみが休暇取得の対象でした。2025年4月1日施行の「育児・介護休業法」では、これらの事由に加えて「子どもの入園式・卒園式の出席」「学級閉鎖時の対応」なども新たに休暇事由対象となり、より柔軟に取得できるようになりました。更に休暇を取得できる期間が「子が生まれた日から子が3年生を修了するまで」に延長されました。なお、取得可能日数の変更はなく、対象の子が1人の場合は年間5日間、2人以上の場合は最大年間10日までとなっています。(この1年間は4月1日〜翌年3月31日まで)
2025年4月改正:出生後休業支援給付金が創設されました
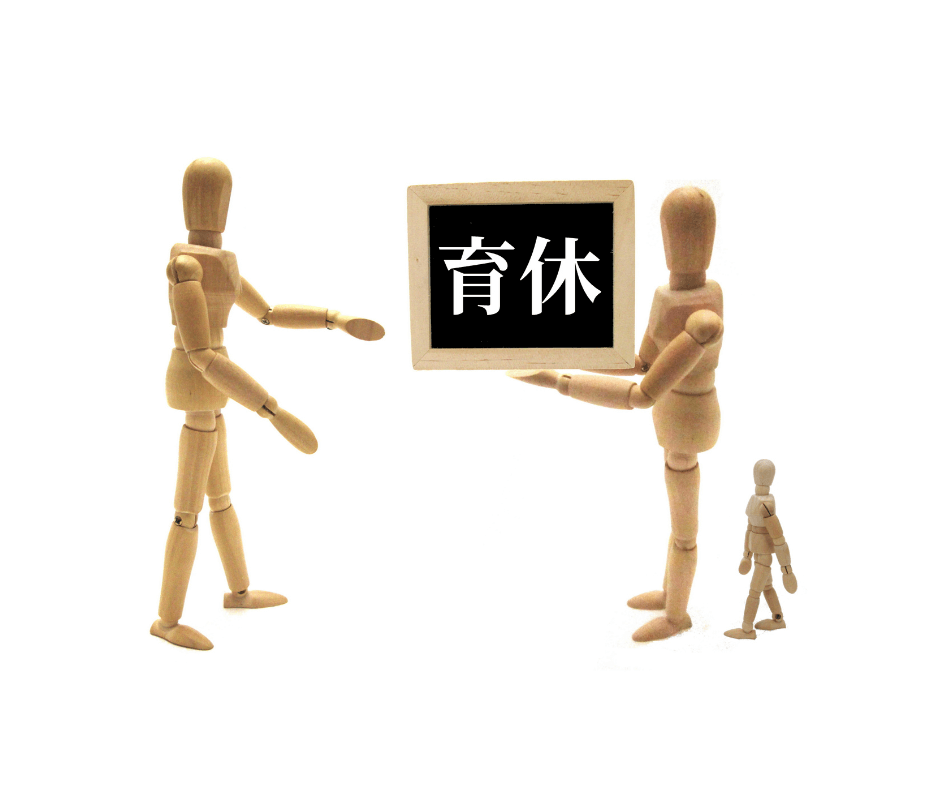
新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。この給付金は、子の出生直後一定期間の内に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の産後パパ育休や育休を取得した場合、既存の「出生時育児休業給付金」又は「育児休業給付金」に上乗せされ、最大で28日間支給されます。育児休業中の収入減を、できる限り抑えることを目的としたこの給付金により、支給要件を満たす対象期間内(説明あり)の育児休業中は「休業開始時の賃金日額の80%相当額(ただし、法律で定められた上限額があります)が支給され、社会保険料や税金の控除後の金額を考慮すると、手取りベースで、実質的には休業前の賃金の、100%相当が受け取れるよう設計されています。(具体的な支給額の上限や支給される期間(日数)については、厚生労働省が定める支給要領に詳細が記載されていますので、必ず最新の情報をご確認ください。)
出生後休業支援給付金:具体的な支給要件
「出生後休業支援給付金」の支給を受けるためには、以下2つの要件を満たしている必要があります。
①雇用保険の被保険者が対象期間中(説明あり)に同一の子について「出生時育児休業給付金」か「育児休業給付金」が支給される育児休業を、通算して14日以上取得したこと。
②雇用保険の被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に、通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または子の出生日の翌日において、配偶者の育児休業を要件としない場合(説明あり)に該当していること。
出生後休業支援給付金:支給額の計算方法
前項支給要件を満たした場合の「出生後休業支援給付金」支給額計算方法は、以下の通りです。
【休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%】
賃金日額:同一の子に係る最初の育児休業の開始前直近6カ月間の賃金総額を180で除した額
支給日数:対象期間における「出生時育児休業給付金」又は「育児休業給付金」が支給される休業の取得日数で、上限は28日
出生後休業支援給付金:対象期間とは

被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)
「出産予定日又は子の出生日のうち早い日」~「出産予定日又は子の出生日のうち遅い日から起算して、8週間を経過する日の翌日」までの期間
被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親かつ子が養子でない場合)
「出産予定日又は子の出生日のうち早い日」~「出産予定日又は子の出生日のうち遅い日から起算して、16週間を経過する日の翌日」までの期間
配偶者の育児休業を要件としない場合とは
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業、フリーランス等雇用される労働者ではない
- 配偶者が産後休業中
- 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
2025年4月に改定された上記以外の主要な制度をご紹介します
残業免除の対象範囲の拡大:3歳までの子供を養育する従業員が利用できる制度とされていた「残業免除」の請求が、小学校就学前の子どもを養育する従業員まで、と対象範囲が拡大され、より多くの従業員が制度を利用できるようになりました。
育児休業等取得率の公表:「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表義務が、従業員1,000人以上の企業から300人以上の企業へと拡大されました。企業が取得率を公開することで、社内外の意識向上と育児支援の風土醸成を目指しています。
2025年4月改正:介護との両立をよりしやすく

介護を担う従業員に対する両立支援への取り組みが、さらに強化されました。今回の改正では「介護休業」や「仕事と介護の両立支援制度」の利用を促進し「介護を理由に、仕事を辞めざるを得ない状況を防止すること」を目的としています。その一環として、企業は40歳に達する従業員に対し「介護休業などの制度に関する情報提供を実施」すること、介護に直面した従業員には「制度等に関する個別周知と制度利用の意向確認の実施」が義務付けられました。これは将来的に介護を担う可能性が高まる年齢層や、介護に直面した従業員に対して、早い段階から制度の理解と準備を促すための仕組みです。具体的には「介護に関する制度の紹介」「介護休業の申し出先、相談先」「介護休業給付金の概要」等の周知・案内が実施されます。なお、松本ESテックでは、一般的には介護休業と同様の事由が求められる「介護休暇」を、社内独自の基準に従い、利用しやすい制度とし、運用しています。
2025年10月改正:柔軟な働き方を実現するための措置とは

2025年2回目となる10月の改正では、厚生労働省が定める「柔軟な働き方を実現するための5つの措置」の中から、企業が2つ以上を選択し、制度として実施することが義務化されました。この措置の対象は「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(小学校入学前まで)」とされ、制度内容の周知に加えて、制度利用の意向を個別に確認することも新たに義務づけられています。厚生労働省が定める5つの措置は以下の通りです。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ養育をすることを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
松本ESテックでは、このうち「養育両立支援休暇の付与」と「短時間勤務制度」を導入し、対象となる従業員への制度説明と意向の確認を実施しました。多くの従業員は「養育両立支援休暇取得」を希望しています。
まとめ

2025年の「育児・介護休業法」改正は、単なる制度の変更ではなく「誰もが仕事と家庭を両立できる社会」への大きな一歩として位置づけられています。厚生労働省がこの改正に踏み切った背景には、依然として男性の育児休業取得率が約30%(令和5年度)にとどまっている現実があります。政府は2025年度に50%、2030年度には85%の取得率を目標に掲げており、男女が共に「育児や介護を担いながら働き続けられる社会の実現」を目指しています。10月の改正で新たに創設された「出生後休業支援給付金」は、安心して育休を取れるようにするための経済的な後押しです。さらに、企業への「取得状況の公表義務」も拡大され、あらゆる面から、従業員が制度を利用しやすい職場づくりを促進しようとする狙いがあります。今後必要なことは、これらの制度が“使われる”ことです。育児や介護が特別なことではなく、自然に社員同士で支え合える職場文化をつくり、企業も従業員一人ひとりがライフステージに合わせて働き続けられる環境整備を進めることが求められています。
【出典・参考】厚生労働省HP「育児休業制度特設サイト」「出生後休業支援給付金を創設しました」「男性の育児休業取得率等の公表について」「こども未来戦略方針(政府の目標設定)」「介護休業制度特設サイト」